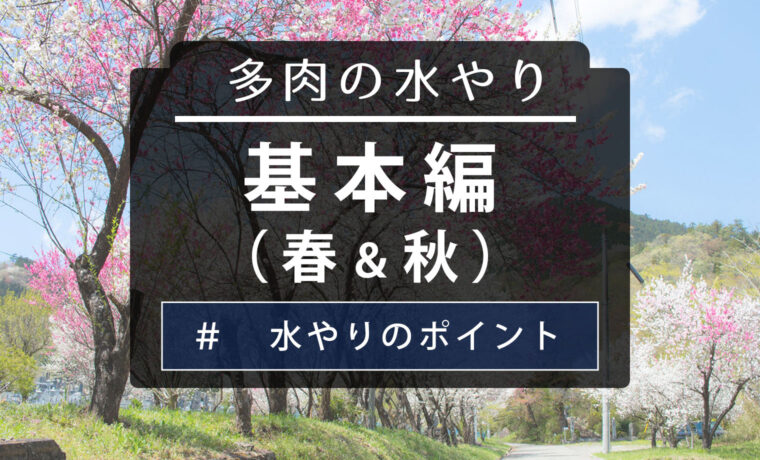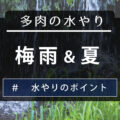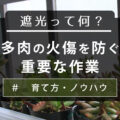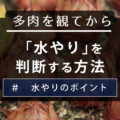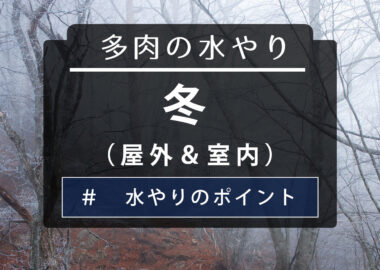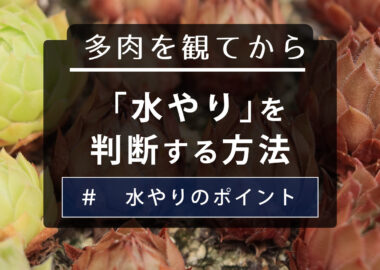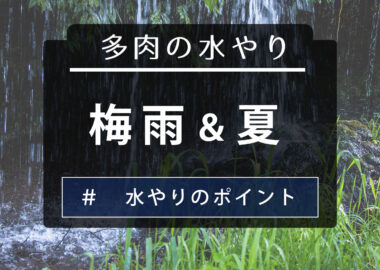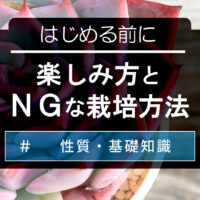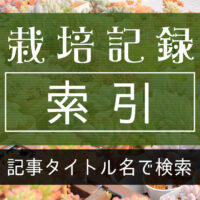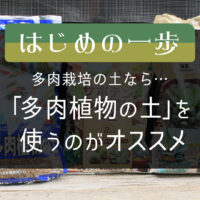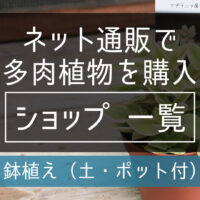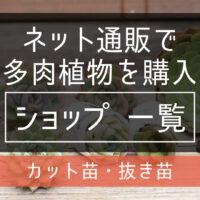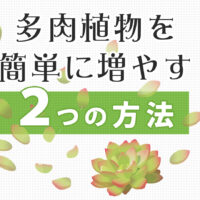この記事では、多肉植物の基本的な「水やり方法」を紹介します。
多肉といっても、他の植物と同様で…
「土が乾いたら、たっぷりと水を与える」です。
難しくはありませんので、
まずは基本となる、普通の水やりを実践して頂けばと思います。
記事の概要
- 水やりの基本は、他の草花と同様
- たっぷりと水を与える
- 次の水やりは、土がしっかりと乾くまで待つ
ポイント
多肉植物の成長シーズンは、主に「春と秋」になります。
この季節に、しっかりと水を与えることで、
水分と肥料を吸って大きく成長します。
ただ、多肉は水分を消費しにくい性質で、水切れにも強いため…
基本的に、毎日水やりを行う必要はありません。
・・・
・・
・
スポンサーサイト
◆ まえおき
対象は「鉢植え」

▲ 2.5号(7.5cm)前後のポット
この記事で、水やりの対象とするのは、
一般的に売られている、2~3号のポットに…
植えられた多肉植物になります。
花壇などの地植えでは、ちょっと感覚が違うので今回は省略とさせて頂きます。
水やり用語
| 灌水【かんすい】 | 作物・植物に対し行う、水やりの事。 散水より限定的。 |
|---|---|
| 水切れ・水下がり | 植物内の水分が不足して、柔らかくなっている状態。 |
| 水揚げ【みずあげ】 | 水切れした植物に水分を供給する作業。 深水や底面給水(腰水)など |
上記の用語は、日常の会話や文章でも使われますので、
覚えておくとスムーズです。
特にブログや植物の説明欄などでは、水やりと同じ意味の…
「灌水」がよく使われています。
・・・
・・
・
▼ 基本の水やり

多肉植物は、観葉植物と同じように…
1年を通して葉を付ける常緑草です。
そのため、水やりも1年を通して行わなければなりません。
水やりは2パターン
- 春 & 秋 & 冬
- 梅雨 ~ 夏
少し話が逸れますが、多肉の水やりには…
大きく分けると「春・秋・冬の水やり」と、
「梅雨~夏の水やり」の2パターンがあります。
季節によって変えざるを得ない
ここでは割愛しますが、特に梅雨~夏にかけては、
水やりを控えてあげないと…
多肉にダメージを与えてしまい、最悪は枯れてしまいます。
そのため「多肉の水やりは難しい」といわれることもよくあります。
梅雨~夏の水やりは、こちら
先に「梅雨~夏の水やり」を知りたい方は、
上記の記事をご覧ください。
「春・秋・冬」のケース

本題に戻りまして、この記事では水やりの基本となる…
「春・秋・冬」のケースを紹介します。
なぜ基本かというと、
春・秋は多肉植物の生育期にあたり、
水やりの基本を身に付けるのに、適したシーズンだからです。
初心者でも綺麗に育つ
特に初春や晩秋では、湿度が低く…
病害虫などのトラブルも発生しにくい期間です。
人によっては、めちゃくちゃ簡単に感じられるかもしれません。
多肉デビューも「春・秋」がオススメ
この時期は、水やりが簡単で多肉もよく増えます。
そのため、はじめての多肉栽培なら「春・秋」がオススメとなります。
冬も基本的には同じ
多くの多肉は、冬の間は成長期ではないのですが、
水やりの感覚としては、春・秋と同様です。
水やりルール

観葉植物でも、季節の草花でも…
水やりのルールは、だいたい下記の2つになります。
- 鉢底から水が流れるまで、たっぷりと与える
- 土が乾いてから、水を与える
なかにはイレギュラーもありますが、基本はどれも同じです。
多肉植物の水やりも同様
少ない水でも生きられる多肉ですが、
主に成長期での水やりは、他の植物と同様で…
土が乾いてから、たっぷりと与えればOKです。
引き続き「春・秋・冬の水やり」について、もう少し詳しく紹介します。
・・・
・・
・
スポンサーサイト
❶ たっぷりと灌水

多肉植物であっても、一般的な水やりのイメージと同じです。
ジョウロや水差し、シャワーを使って…
上からサーっと、たっぷり水をかけます。
鉢底から流れるまで続ける
たっぷりとは「鉢底から水が流れるまで、しっかり与える」という事です。
さらに、5秒ほど流し続ければ…
ポット(土)の隅々まで保水されやすくなります。
目的は保水させるため
たっぷりと水を与える理由は、土に水分を含ませるためです。
当たり前といえば当たり前なのですが、
土の表面が濡れる程度の灌水では、土に水分が残らない為、
根から十分に吸い上げることができません。
肥料も一緒に吸ってくれる
土にたっぷりと水分が含ませれば、
土に溶けだした肥料も一緒に吸い上げてくれます。
ですので、成長期の春・秋では、
しっかりと灌水することが重要になります。
エケベリアは少し気を遣う

エケベリア属の多肉は、そのフォルムの特徴から…
上から水をかけると、ロゼットの中心に水が残り、
水だまりを作ってしまうケースがあります。
セダムなどは、葉が丸っこいので大丈夫
放置すると、蒸れたり傷む可能性がある
この水だまりを放置しても、大丈夫なことが多いのですが…
直射日光が当たる夏の炎天下で放置すると、
葉が傷む可能性があります。
株の周りに灌水

対策としては、水を与える際は…
水差しを使い、株の周りに灌水します。
もしロゼットに残ってしまった場合は、
ポットを振ったり、ブロワーなどで水滴を弾き飛ばします。
1ポイントアドバイス
多肉の数が増えてくると、意外と水やりに時間を取られます。
エケベリアを多く管理しているなら、
なるべく二度手間を避けるため、水だまりができないよう…
株の周りに灌水するのがポイントです。
面倒なら遮光して管理

「水滴を飛ばすのが面倒くさいなぁ~」という人は、
日よけを使って遮光をしておきます。
直射日光が当たらなければ、水滴が残っていても、
ほぼダメージを負わずに乾いてくれます。
遮光に関する記事はこちら
水滴を残さないメリット

水滴を常に残してしまうと、洗車と同じで…
乾燥したあと、水垢のように目立ちやすくなります。
水滴を残さなければ、美観を保ちやすいメリットがあります。
微塵の排出

▲ 水やりで排出された微塵
市販の培養土など購入すると、種類にもよりますが、
微塵【みじん】という…
土が砕けた小さな粒が含まれています。
赤玉土や鹿沼土が、やがて微塵になる

左:通常 / 右:微塵
培養土には、赤玉土や鹿沼土がよく混ざっており、
これらが水やりなどで崩れ、やがて微塵になります。
微塵が増えると空気の流れや、水はけが悪化してしまいます。
灌水で排出できる
植替え後に、微塵が混ざっていたとしても、
たっぷりと水やりを行えば、微塵を排出させることができます。
茶色の水が透明に変わるまで、水を与え続けるのがポイントです。
2年に1回ほど植替えれば問題なし
重要そうな気もする微塵の話ですが、
実際のところ、市販の培養土なら微塵を気にする必要はなく…
大きな悪影響を及ぼすこともありません。
基本通りの灌水をしていれば、
2年に1回ほど、新しい土を使って植替えれば大丈夫です。
【まとめ】がっつりと水やり
なんだかんだ書いてきましたが、
基本はがっつりと水を与えればOKです。
春・秋の成長期なら、多肉は元気に大きく育ってくれます。
・・・
・・
・
スポンサーサイト
❷ 土が乾いたら灌水
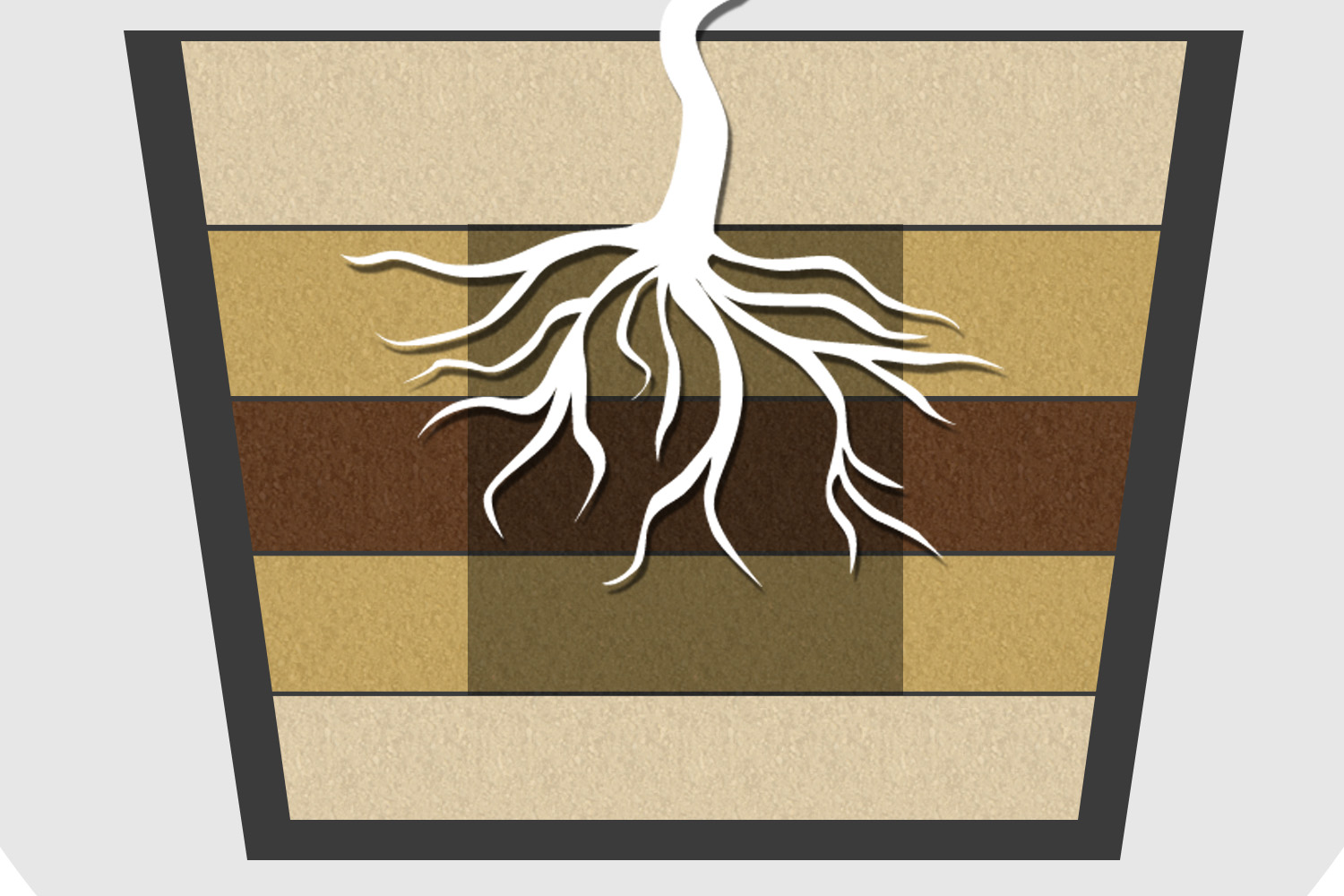
続いて、水やりをした後…
次は「いつ水やりをするのか?」になりますが、
こちらも他の植物と同じように、
土が乾いたら、水やりをすれば大丈夫です。
土が乾いた目安は?

慣れないうちは、土の中まで乾燥した状態を…
外から確認するのは意外と困難です。
根が張っている多肉であれば、ポットから簡単に外せるので、
目視で確認してみるのが確実です。
だいたい、3日~2週間ほどで乾燥する
ちょっと日数に開きがありますが、
乾燥して晴れた日なら3日程度で、
梅雨時などでは2週間ほどかかる場合もあります。
また、使用する培養土やポットによっても変わるため…
このあたりは、少しづつ自分の環境で覚えていく必要があります。
前後したらダメなの?
例えば、極端に水やりのタイミングが前後したら…
多肉植物はどうなってしまうかというと、
早過ぎれば徒長しやすく、遅過ぎると葉にシワが寄ったりします。
遅れたほうが上手くいく

左:正常 / 右:徒長
もし、梅雨のような曇天が続く期間に…
早過ぎる水やりをすると、多肉は徒長してしまいます。
ですが、水切れに強い多肉は、
1ヵ月以上、水を切っても枯れることはありません。
また、状態も直ぐに回復します。
そのため、多肉の水やりは遅らせたほうが上手く育てられます。
水やりサイン

繰り返しになりますが、
多肉は本当に水切れに強い植物なので、
葉にシワが寄ったり、少し垂れ下がった状態となる…
「水やりサイン」を見てからでも十分に間に合います。
ここまで待てない人のほうが多い
多肉植物の場合は、土はカラカラでも…
水切れしていない状態も多いので、
初心者の方では、水切れまで待てない場合も多いかと思います。
日数での灌水は非推奨
例えば「水を与えてから5日後」とか…
「土の表面が乾いてから2日後」など、
日数を目安にするのは、なるべく早く卒業したほうが無難です。
応用が効かない
それは、ポットのサイズが違えば、土の量が変わり、
乾燥するスピードも異なってくるからです。
また、苗のサイズによっても多肉自体の保水力が違います。
そのため、次の灌水を日数でカウントするより、
多肉の状態で見極めていくほうが、栽培の応用が効くようになります。
多肉を観れば判断できる

水やりの上手い人は「何を見ているのか?」というと…
土の乾燥具合ではなく、多肉の状態を観ています。
そのほうが「灌水が必要か、否か」の判断が付くからです。
多肉を観てから灌水する方法はこちら
・・・
・・
・
スポンサーサイト
【まとめ】ちょっと我慢が丁度いい
多肉植物の場合、経験が少ないと…
水やりのスパンは早めになってしまいます。
そのため、自信が付くまでは、
3日程度、遅らせると丁度いいかと思います。
また、遅めに慣れておくことで、
梅雨~夏の水やりにもスムーズに対応しやすくなります。
梅雨と夏は、イレギュラー
梅雨と夏は、水やりを減らすイレギュラーな期間です。
そのため「春・秋」より、水やりはシビアになります。
・・・
・・
・